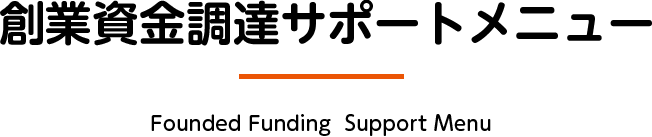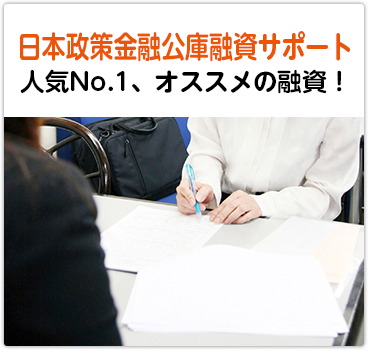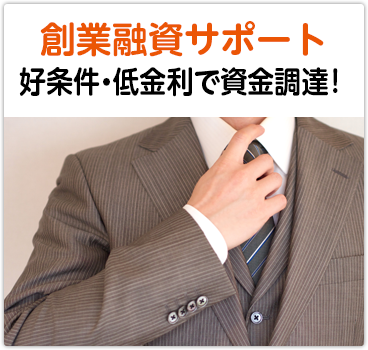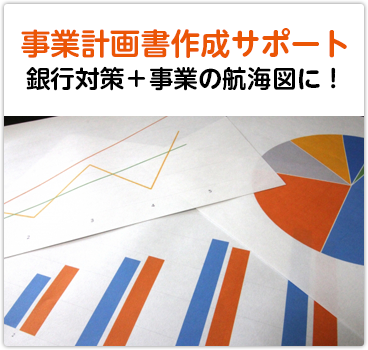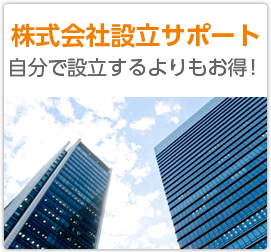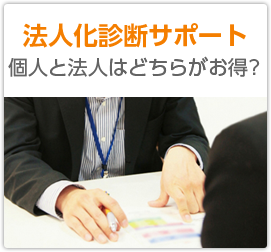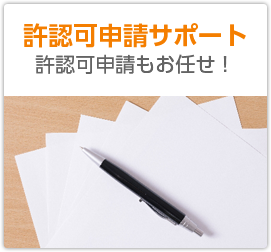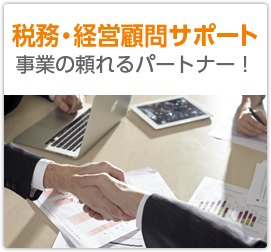神戸市で税務調査に備えるなら?税理士に相談するメリットと注意点

税務署から税務調査の通知が届いたとき、多くの方が強い不安を感じます。
特に神戸市や周辺地域の中小零細企業の経営者、経理の方や個人事業主からは、
- 「どんな点を調べられるのか分からない」
- 「対応を誤って余計な追徴課税を受けないか心配」
- 「顧問税理士がいないので準備方法がわからない」
- 「調査官からどんな質問が来るかわからない、どう回答したらいいかもわからない」
- 「今まで民商でやってきたけど、民商が対応してくれない」
といった声が多く寄せられています。
実際、税務調査は規模や業種を問わず実施される可能性があり、日頃から帳簿を整えていても調査官への対応や質疑応答を一人で乗り切るのは簡単ではありません。
こうした状況で頼りになるのが、税務調査に対する経験が豊富な税理士のサポートです。
税務調査の現場に立ち会い、税務署とのやり取りを代理し、必要に応じて交渉まで担ってくれるため、精神的にも実務的にも大きな安心につながります。
神戸市での税務調査の実態とは

税務調査は全国的に行われており、もちろん神戸市の事業者も例外ではありません。
税務署は申告内容の正確性を確認するため、必要に応じて法人・個人を問わず調査を実施します。
特に調査対象となりやすいのは、以下のようなケースです。
- ・売上規模が急激に変化している場合
- ・経費計上が不自然に多い場合
- ・申告内容と実際の取引に乖離があると見られる場合
- ・無申告や期限後申告が繰り返されている場合
- ・申告書に税理士の署名が無い(顧問税理士がいない)場合
また、中小企業や個人事業主に対する調査では、大企業と異なり帳簿や領収書の管理体制が不十分であることが多く、調査官から何らかの指摘を受けやすい傾向にあります。
実際、神戸市内の事業者からも「思っていた以上に細かい点を確認された」という声が少なくありません。
税務調査は決して「悪いことをしているから入るもの」とは限らず、あくまで税務署が適正な申告を確認するための手続きです。
しかし、対応の仕方次第で結果が大きく変わることもあるため、事前準備や専門家のサポートが重要になります。
また、もちろん「悪いこと(不正取引)をしている証拠をつかんで調査に来る」ということもあります。
この場合は当然、追徴金額を免れることは無いですが、対応によって金額は十分変わります。
経験豊富な税理士に調査立会から関与してもらう方が良いと思います。
税務調査の流れとチェックされやすいポイント
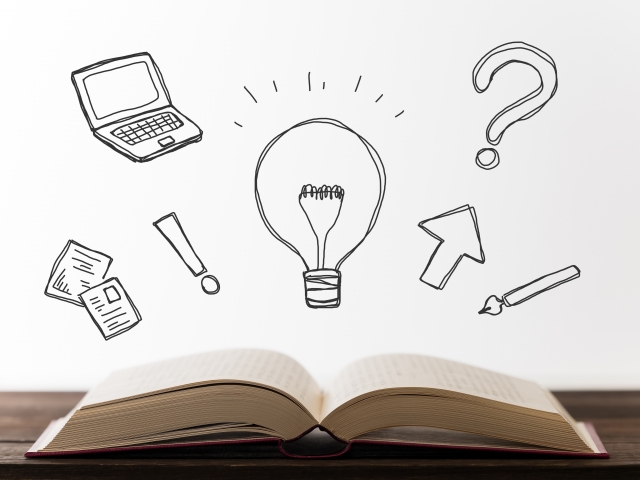
税務調査は、通常の場合は事前通知から実地調査、結果説明までの流れで進みます。
神戸市の事業者の場合も、全国と同様の手順が取られます。
※例外として全調査の5%程度は抜き打ちの無予告調査もあります。
事前通知から実地調査までの流れ
- 事前通知:税務署から電話や書面で連絡があり、調査日程や対象年度が伝えられます。
- 準備期間:帳簿や領収書、契約書、請求書などを実地調査に向けて準備します。事前に帳簿データの提出を求められることもあります。
- 実地調査:調査官が事務所や店舗に来訪し、原始証憑と帳簿との確認やヒアリングを行います。
折衝期間:実地調査を踏まえて税務署内での内容検討、不正が無いかの確認等(反面調査)が行われます。必要に応じて調査官から呼び出されることもあります。 - 結果説明:調査終了後、申告内容に問題があればその内容の指摘や修正申告の案内があります。場合によっては重加算税についての案内もあります
上記の流れの中では折衝期間が一番長くなりやすく、また一番大変な箇所になります。
調査官が注目する主なポイント
- 売上の計上漏れ:現金売上の計上漏れ、売上の計上時期のズレ(期ズレ)など、間違いや不正が起こりやすい箇所を重点的に確認されます。
- 経費の妥当性:私的利用と業務利用の線引きが曖昧な経費(接待交際費、会議費、消耗品費、雑費など)が見られやすいです。また不正あるいは架空の経費(主に外注費、給料手当など)が無いか?も確認されます。
- 帳簿と証憑の整合性:帳簿に記録された金額と領収書・請求書が一致しているか、不審な領収書(特に現金取引)が無いか?を細かく確認されます。
無申告や修正申告の扱い
もし申告漏れや誤りが発覚した場合には、修正申告を求められ、過少申告加算税・延滞税がかかります。
また、悪質と判断されれば調査対象期間の延長(5年もしくは7年まで遡る)や重加算税が課される場合もあり、事業に大きな負担となる可能性があります。
こうしたリスクを避けるためには、日頃から正確な帳簿管理を行い、必要に応じて税理士に確認してもらう体制を整えておくことが重要です。
税務調査で起こりがちなトラブルとリスク
税務調査では、申告内容の確認だけでなく納税者本人の対応が結果に大きく影響します。特に専門知識がないまま一人で対応すると、次のようなトラブルが起こりやすくなります。
調査官とのやり取りでの対応ミス
不用意な発言や、必要以上の情報提供をしてしまうことで、本来指摘される必要のなかった点まで調査が広がるケースがあります。
質問には正確かつ適切に答える必要がありますが、慣れていないと難しいものです。
帳簿不備による追徴課税
領収書の紛失や記帳漏れなど、小さな不備でも「経費として認められない」と判断されることがあります。
この場合も反論の仕方によっては必ずしも経費として認められないわけではありません。
ですが、対応を誤った結果、納税額が増加し思わぬ追徴課税につながる可能性があります。
延滞税・加算税のリスク
修正申告が必要になった場合、追徴の納税額だけでなく延滞税や過少申告加算税、重加算税といった罰金が課されることがあります。
特に重加算税においては賦課の要件がしっかりあり、その法律的な要件が分かっているかどうか?の違いは大きいです。
ですが、一般の方だとわからないまま、調査官に適切な反論もできないまま、重加算税がかかってしまうリスクもあります。
一人での対応の限界
税務調査は専門的な知識と経験が求められる場面が多く、一人で対応すると心理的にも大きな負担となります。
結果として不利な状況に追い込まれるリスクも高まります。
こうしたトラブルを未然に防ぐためには、税理士の立ち会いを依頼し、調査官とのやり取り、交渉などを任せることが最も有効です。
税理士に依頼するメリット
税務調査において、税理士のサポートを受けることには多くの利点があります。
専門的な知識と経験を持つ税理士が関与することで、調査の進め方や結果に大きな違いが生まれることも少なくありません。
税務署との窓口を任せられる安心感
税務調査では、調査官とのやり取りや質疑応答が重要になります。
税理士が立ち会えば、納税者に代わって税務署との窓口を担い、適切に対応してくれるため、精神的な負担が大幅に軽減されます。
交渉力・専門知識による追徴リスクの軽減
税理士は税法に基づいた判断を行い、必要に応じて調査官と交渉を行います。
その結果、本来認められるべき経費や処理が適切に反映され、追徴課税のリスクを減らすことにつながります。
調査後の改善提案が受けられる
調査が終わった後も、税理士は今後の申告や帳簿管理について改善提案を行ってくれます。
これにより、次回以降の調査リスクを抑え、日常的な経理業務の精度向上にも役立ちます。
結果的にコスト削減になるケースも
税理士に依頼する費用は発生しますが、追徴課税や加算税を未然に防げることで総合的にコスト削減につながるケースも多くあります。
安心して事業に専念できる点も大きなメリットです。
税務調査に不安を感じる場合には、専門家に依頼することが最も効果的なリスク対策となります。
神戸市で税務調査に強い税理士を選ぶポイント

税務調査に備えて税理士を依頼する際には、どの事務所に相談するかが重要です。
税務調査対応の経験や姿勢は事務所ごとに異なるため、以下のポイントを意識すると安心です。
地域に根ざした事務所であるか
神戸市や兵庫県内に拠点を持つ事務所は、地元の事例や税務署の傾向に詳しい場合が多く、スムーズな対応が期待できます。
また対応税理士は、税務調査中は企業や個人事業主等の納税者に代わり何度となく税務署に行く必要に迫られます。
あまり遠方だと、そのような対応をしてくれない、追加の費用がかかる(そもそも費用がかなり高い)、などがあり得ます。
そういう意味では、全国対応を謳う税理士より地元の税理士の方がおススメです。
税務調査対応の実績があるか
顧問税理士が付いている法人や個人事業主の税務調査の発生率は元々高くありません。
なので、通常の税理士は1年を通して1件も税務調査を対応しない、対応しても1~2件ということも珍しくないです。
そういう意味では税務調査は特殊な場面であり、単に税理士というだけでなく、調査経験が豊富な税理士に依頼することが重要です。
過去の税務調査の経験数、経験した税務調査先の事業規模や金額など、どのような経験をしてきたか?を確認するのが良いでしょう。
費用体系が明確か?適正な範囲な料金であるか?
規模の大きな全国対応を謳う税理士や、国税出身などのブランドを謳う税理士などでは、最低料金でも調査報酬100万円~かそれ以上というかなり高額な費用を請求する事務所もあります。
対応内容・サービスの良しあしはともかく、その料金体系ではかなり大きな追徴金額(例えば1000万円以上)のリスクを感じているような方、税務調査の中でも査察が入っているような方以外はそもそも費用が合いません。
普通の中小零細企業や個人事業主の方ではあれば、もう少し安価で適正な範囲で対応してくれる税理士を探すことをおススメします。
そのためにも契約前に料金体系を明示してくれる事務所を選ぶことで、予期せぬ費用トラブルを避けられます。
相談のしやすさ
初めての税務調査では、気軽に質問できる環境が大切です。
電話やラインのやり取りだけなど、顔を合わせないで契約をすることは避けた方が安全です。
なので、初回無料面談やオンライン相談に対応している事務所なら、より安心して依頼できます。
これらのポイントを押さえて選ぶことで、調査への対応だけでなく、その後の経営や税務処理においても心強いパートナーとなるでしょう。
税務調査を受ける前に準備しておくべきこと
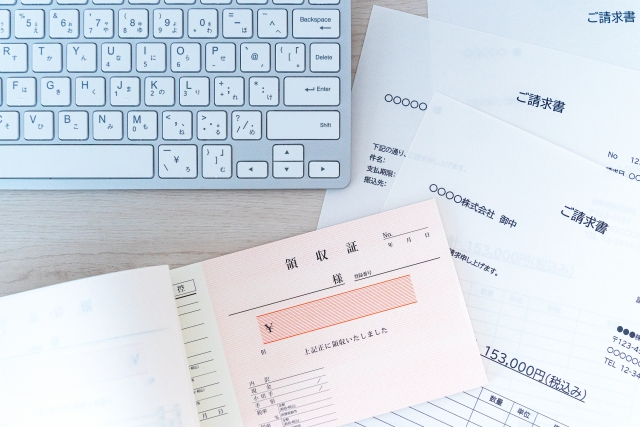
税務調査に備えるためには、日頃からの帳簿管理に加え、事前の準備が大切です。
調査官が訪れる前に以下の点を整えておくことで、スムーズな対応が可能になります。
帳簿・領収書の整理
調査では帳簿と証憑類の整合性が最も重要視されます。
領収書・請求書・契約書などを年度ごとに整理し、紛失している証憑が無いか?など確認しておきましょう。
申告内容の再確認
過去の申告内容を見直し、売上や経費の記載に誤りがないかを確認することが必要です。
特に売上や仕入れ・外注費、現金取引などは指摘を受けやすいため、問題ないか念入りに点検しておきましょう。
想定問答の準備
税務調査では調査官から質問を受ける場面があります。
例えば「この経費の内容は?」「この売上は計上したか?」「申告書はいつ、誰が、どのように作成したか?」などです。
税理士から想定問答を聞いて、事前に準備しておくことで、スムーズに答えられるようになります。
税理士への事前相談
不安な点があれば、事前に税理士に確認してもらうことが有効です。
第三者の視点で申告内容を点検してもらうことで、調査当日のリスクを大幅に減らすことができます。
また、事前にどのようなリスクがあるか?を知ることもできます。
これらの準備をしておくことで「どんな目に合うかわからない!」といった漠然とした税務調査に対する不安を軽減し、落ち着いた対応が可能になります。
よくある質問(FAQ)
税務調査はどのくらいの頻度で行われるのですか?
税務調査は毎年必ず行われるわけではありませんが、申告内容や事業規模、業種によって数年に一度の割合で対象になることがあります。
特に売上の変動が大きい場合や、帳簿の不備が疑われる場合、最初の税務調査の際の態度等で再度不正申告を行う可能性が高いと思われた場合、このようなときに税務調査が実施されやすくなります。
顧問税理士がいなくても対応してもらえますか?
はい、可能です。
顧問契約がなくてもスポット対応を依頼できる税理士は多く存在します。
むしろ、顧問税理士がいない方は税務調査の直前や通知を受けてからあわてて相談するケースが多いです。
税理士に依頼すると費用はどれくらいかかりますか?
費用は事務所や依頼内容によってかなり異なります。
顧問契約の場合は顧問料に含まれることもありますが、スポット対応の場合は数十万円~数百万円、成功報酬制(税額減少の割合で報酬決定、一般的に高額なことが多い)など全く違います。
あまり高額な費用(数百万円)だとコストのデメリットが大きくなるかもしれません。
ただ、数十万円の範囲であれば小規模な法人、個人事業主の方でもコストより安心感や追徴課税を避けられるメリットの方が大きい印象です。
税務調査では必ず追徴課税を受けるのですか?
必ずしもそうではありません。
帳簿や申告内容に大きな誤りがなければ指摘なし(申告是認)で終了することもあります。
ただし、国税庁のホームページで発表されている「令和5年度の調査事績の概要」から見ると、何らかの非違(追徴課税)があった割合は
法人税 約76%
所得税 約84%
と非常に高確率で何らかの指摘をされている状況が伺えます。
まとめ
税務調査は、法人・個人を問わず事業を行っていれば誰にでも起こり得る手続きです。
神戸市でも中小企業や個人事業主を対象に毎年税務調査が行われており、適切に対応しなければ追徴課税や加算税といった大きな負担につながる可能性があります。
また、税務調査の連絡が来てから本業が手に付かず、仕事が止まってしまう方もいます。
しかし、税理士に依頼することで、税務署とのやり取りを任せられる安心感や専門的な交渉力による無用な追徴税額のリスク軽減を図ることができます。
また、調査後の顧問契約により、将来的な調査リスクを抑えることも可能です。
大切なのは、一人で抱え込んで慌てるのではなく、専門家への相談とそのアドバイスに従った準備を行うことです。
これにより、不安を最小限に抑え、安心して事業に集中できる環境を整えることができます。
無料相談のご案内
税務調査に対する不安を一人で抱え込む必要はありません。神戸市や兵庫県内で多数の事業者をサポートしてきた税理士が、あなたの状況に合わせて適切に対応いたします。
初回相談は無料で承っておりますので、些細なことでもお気軽にご相談ください。事前準備の段階から立ち会い当日の対応、調査後の改善提案まで、安心して任せていただけます。
創業融資専門家コラムの最新記事
- 起業の悩みは一人で抱えない!おさえるべき相談ポイントを徹底解説!
- 税理士を変更すべきタイミングとは?失敗しない乗り換え方と選び方を徹底解説!
- スタートアップ成功のカギは税理士にあり?起業時に頼るべき理由と支援内容を徹底解説!
- 神戸で融資を受ける時に税理士のサポートを受けるメリットやポイント
- 神戸で日本政策金融公庫の融資を受ける方必見!完全利用ガイド!
- 日本政策金融公庫の融資に失敗したら? 創業時の融資を専門家に依頼した方がよい7つの理由
- 【保存版】知らないとやばい!?日本政策金融公庫への融資が自力で通る人と通らない人の違い
- 日本政策金融公庫は延滞に厳しい!?
- 創業計画書を作る上で重要なポイントと考え方
- 日本政策金融公庫の創業計画書~事業の見通し編~
- 日本政策金融公庫の創業計画書~必要な資金と調達方法編~
- 創業支援貸付利率特例制度【日本政策金融公庫】
- 融資手数料¥0の内容【有料との大きな違い】
- 家賃支援給付金【コロナ対策 第2次補正予算】
- 新型コロナウイルス感染症特別貸付【信用保証協会融資】史上初の無利子貸付!
- 新型コロナウイルス感染症特別貸付【日本政策金融公庫】
- 日本政策金融公庫以外での1.05%の低利創業貸付制度!
- 日本政策金融公庫の消極的な融資分野
- 預金残高はどれくらいあれば良いか?
- 経営力向上計画の認定は日本政策金融公庫融資や信用保証協会の保証付融資で有利なのか?
- 日本政策金融公庫と民間金融機関(保証協会付融資)の協調融資のメリット・デメリット
- 日本政策金融公庫の面談でのチェックポイント
- 開業・創業時の自己資金はどこまで認められるのか?(日本政策金融公庫融資)
- IT導入補助金(平成30年度)の最新情報
- 日本政策金融公庫融資を99%成功させるポイント
- 公庫から融資を受ける場合についてくる公庫団信とは?
- 信用保証協会融資の注意点(日本政策金融公庫との違い)
- 公的機関などの無料相談と有料サポートの違い
- 損益分岐点とは?
- 日本政策金融公庫が見ている意外な項目
- 節税or資金調達による事業拡大か
- 平成29年度予算による融資制度の拡充(日本政策金融公庫)
- 日本政策金融公庫と銀行の違い
- 金融機関との付き合い方
- 借りられるけど借りる必要のないときは?
- 金融機関の融資姿勢と融資状況(中小企業向け)
- 会社設立の基礎知識
- MFクラウドファイナンス
- 無担保融資と有担保融資
- 融資の難易度
- 創業融資でやってはいけないこと
- クラウドファンディングとは? その2
- クラウドファンディングとは? その1
- 日本政策金融公庫融資に必要な時間
- 創業融資を受けたい4つの理由と注意点
- 金融機関が融資で見るポイント 貸借対照表編
- 金融機関が融資で見るポイント 損益計算書編
- 創業融資の申請金額の決め方
- 決算での節税+銀行(融資)対策 中小企業倒産防止共済
- 美容業・理容業・飲食業 必見の低利融資!
- 赤字企業での融資対応事例
- 金融機関の選び方
- 原価管理 その2
- 原価管理 その1
- 役員報酬の決め方 その1
- 役員報酬の決め方 その2
- 創業融資 創業計画書(事業計画書)の書き方
- クラウド会計は良いのか?
- 日本政策金融公庫の融資最新情報
- 借金は良いか?悪いか?
- 創業融資 自己資金編 その2
- 創業融資 自己資金編 その1
- 資金調達を検討する際の注意点
- 青色申告のメリットとデメリット
- 起業時に最低限提出す書類(税金関係)